
前にも書いたのですが、自分が写真を撮ってきて、作品と呼べるものがない。
そこで、作品を残していくにはどうすればいいか?考えることにしましたのですが…
作品ってどうやって撮ればいいのか?
何かに絞って撮ればいい…と、ちょっと安易に考えていたのですが、意外に難しいことがわかってきました。
そこで、写真作品の撮り方について調べた途中経過をメモしておきたいと思います。
コンテンツ
写真作品ってどんなものだろう?
まず、初めに、写真作品ってどんなものがあるだろう?ということ。
ここから始めていきましょう。
例えば…
・近江鉄道に絞って様々なシチュエーションを撮る。
・モノクロで撮るポートレート。
・ロードムービーのように車で地方を回ってニューカラーな街を撮る。
・佐内正史のように「わからない」を撮る。
・「ベーコンアイスクリーム」なスナップ集。
・ベッヒャーみたいにタイポロジーの切り口で撮る。
・澤田知子みたいに変身する自分を撮って作品性を出す。
・地元の祭りを撮り続ける。
・家族を撮り続ける。
・多灯ライティングでコスプレ撮影を極める。
・パリの街を撮りに行く。
・グルスキーみたいにコンピューター処理して仕上げる一枚写真。
・ソールライターみたいに家の周りの街をおしゃれにスナップ。
・鬼海さんのPERSONAみたいに同じ場所で人を撮り続ける。
…
こんなふうに、世の中にはたくさんの切り口の写真作品がある。
こんな感じで自分の切り口を見つけて写真を撮りためる。
そんなことをやってみたいものです。
しかし、切り口をみつけるのは簡単ではない…。
謎が多い写真作品制作
この中で気になるものがあるのです。
それは、難解な写真。
発売されている写真集を見ても、その良さがわかりにくく、一枚一枚を見ても、きれい!とかすごい!とかいう写真でもない。
これは、何を伝えようとしているのかが全くわからない。
しかし、そういう写真集が有名な賞を取ったりもしている。
これはどこが評価されたのだろう?素朴で大きな疑問を持つようになりました。
そういった難解な写真集は、どのように撮られているのだろう?
どこが評価されているのだろう?
昨年から、自分の作品というものを撮ってみたくなって、こういうことを調べて始めたところ、
簡単にはわからないのだけど、いろいろなものを当たっているうちに、おぼろげな形が見えてきた。
難解な写真作品
では、難解な写真とはどんなものか?
直接的でない難解なテーマの写真作品とはどんなものかというと…。
例えば、佐内正史。
佐内さんの写真を見ると、事務所に置いてある観葉植物の植木鉢や、実家の和室みたいな、たわいのないものが中判カメラで撮られている。
これらは、意味合いや見た目で、特にテンションが高いわけでもなく、只々なんでもない場面が淡々と撮られている。
なんでもないものを克明に撮る行為が、ひたすら謎で、見ていて苦しくなってしまう。
これは、なんなのか?
この写真作品は何を言おうとしているのか?
どのようにして作られているのか?
作品の撮り方を調べる
その写真作品にはどういう意味があるのだろう?を考えると、そもそも、どういう風に撮られたのだろう?という疑問が湧いてくる。
写真作品の撮り方を知るために、作品の解説や作家自身のインタビュー、作品の制作法そのものについてかかれているテキストをネットを中心に漁ってみたところ、いくつかのヒントらしきものがあった。
2BChannelでは
渡部さとるさんのやっている写真Youtubeチャンネルでは、写真集の解説も多く、作家がどんな風に撮っているかのエピソードも語られる。
その中で、自身の写真作品の制作について語っていることがあった。
撮った写真を20枚セレクトする。セレクトは写真のグループを作る感じで、仲間外れを落としていく。
次に撮ってきた写真を20枚セレクトし、前の20枚と付き合わせ、仲間はずれを落としていき新しい20枚のグループをセレクトする。
こうして、この作業を続けていくと、ある時これ以上他の写真を寄せ付けない完璧な20枚が出来上がる時が来る。
これを個展で展示している…という。
また、いわゆる「上手い写真」というのは避ける…とも言っていて。
「上手さを捨てた写真」というのが良くて、しかし難しい。
これが、セレクトしたグループの中で邪魔になってくる。が、つい入れてしまうとセレクトを失敗することになる…というような話もあった。
写真学生の場合
これも2BChannelでの話。
チャンネルでは、今、写真学校に通っている学生を取材している。写真学校では普段どんなことをやっているのかが学生の口から語られる。
学生は、ひと月の間自分で写真を撮りためてプリントをする。それを50枚、100枚といった感じで、結果をまとめて先生に見てもらう。
学生が見せてくれた写真は、彼の生活圏内・身の回りを撮った写真で、かっこいいとか劇的とかいうものではない淡々としたもの。
先生たちは、それを見て、良い、良くない、流れてる…などの言葉で評価するらしい。
言われている学生は、それのどこが悪かったり、今回どこが良かったのかわからない様子で、あれこれと評価を想像する。禅問答のよう。
この写真を見ている先生の一人が、赤々舎の姫野さんという方で、この方の編集した写真集は木村伊兵衛賞を取ったりする…そんな方。
これまで膨大な量の写真を見てきた姫野さんが見て、これは良い・良くない…と評価する。
それは良い加減なものではないと渡部さんは言う。
川内倫子の場合
昨年から行われている川内倫子さんの個展では、展示会図録にインタビューが載っていて、幾らかの答え合わせができる感じだった。
川内さんは、生活の中や世間で気になるものを写真に撮っている。それは子供が捕まえてきたヘビだったり、アイスランドの休火山だったりする。
インタビューの中で、ある作家の本からインスパイアされていると言っている。それは宇宙、人類、自然、科学、摂理…などに関する内容。
そういった考え方や視点を持った上で、川内さんは気になるモノを撮っているらしい。
それが作品になっている…と聞くと、作品制作の構造が少し見えた気がする。
これらを頭に置いて写真作品制作をまとめてみる
・思想を持つこと。これに変わること(考えや気分)でも良い。
・撮影対象は「気になるモノ・コト」。
・気になる対象は、時間をおいて、距離を変えて、執着して撮る。
・撮影する時点でなぜ撮るのかは気にしなくて良い(戦略は必要ない)。
・撮れた写真を見渡して、同じグループでまとめる。
・キャッチーな写真は別に退けておく。
・一枚で語るというより、グループで意味を醸し出すイメージ?
・ここで、自分が何を撮ろうとしていたのかを分析する。
・そして、グループ化した写真たちの意味づけをする。
・テーマがはっきりする。
・それに沿って微調整をする。
・ステートメントを書く。
・自分のコンテキストを考え、最初に戻る。
・繰り返して作品の制作とする。
このなかで、一枚一枚をどう撮るか?(かっこよく?平然と?)がある。
かっこいい写真は撮りたいけれど、見渡してみると平然とした写真がいいような気がする。
テーマ・ステートメント・コンテキストの位置が気になるが今回は後半で。
では、私はどうするのか?
これが、半年ほど調べて分かってきたこと。
色々な写真集・写真展示のあちこち一部分にかするような感じで、作品制作が見えてくるような気がする。
でも、これをもって自分の作品作りを始めたい…とはいかない。
実際は、自分の身の回りに起こっていることしか撮れない。
もしくは、興味のあるコト・モノのある場所まで飛んでいかないといけない。
また、思想や考えや気分を反映できる対象物というのは、なかなか見つからないかもしれない。
それを見つけ出せるようになる訓練が必要だと思う。
まずはこれかもしれない。
今回は、こんな手順で撮ることを考えてみた。
こんなに難しいことをしなくても、まずコンセプトや切り口を考えて、それに沿って撮る…ということもできる。戦略先行。
撮影が可能なものから逆算して決めるのもいいだろう。
今は、そんなところ…。
この記事を書いた人
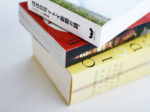
-
地元甲賀内から県内で印刷・web制作、写真撮影などをしています。デザイナー、写真愛好家。
2000年からホームページ・ブログを開始、写真、デザイン、地域...について発信を続けています。ここでは、甲賀市の面白いことを取り上げて記事にしています。特に文化・芸術・カフェ・地域振興のことが多めです。
FUJFILMのカメラ愛好者。PHaT PHOTO100Point達成。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)















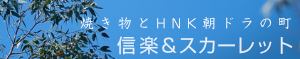
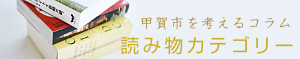

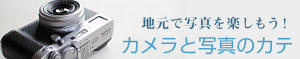


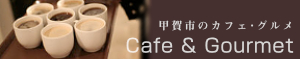


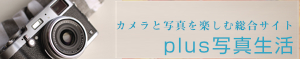
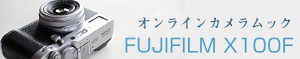

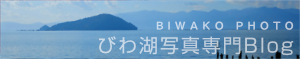







この記事へのコメントはありません。